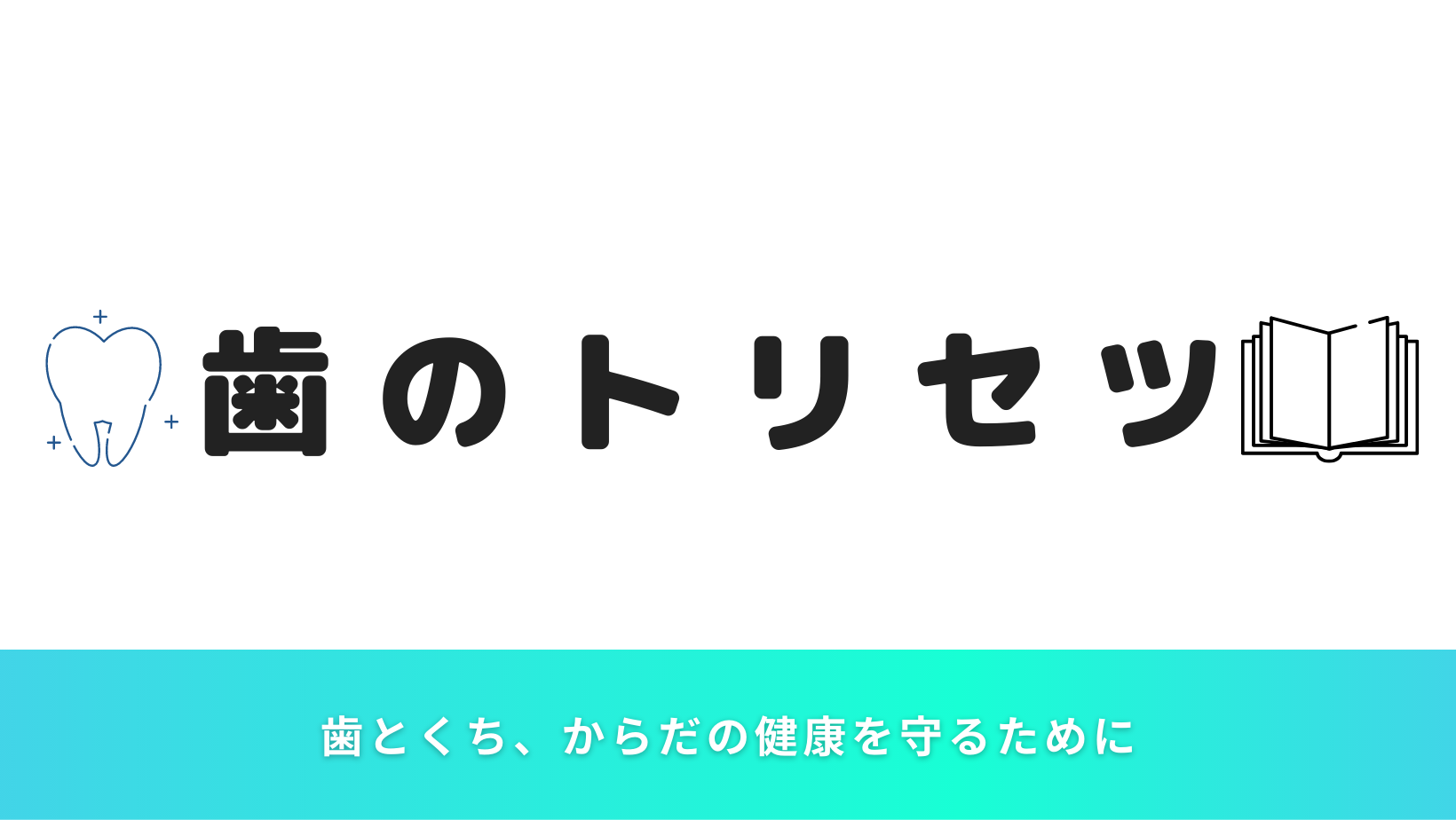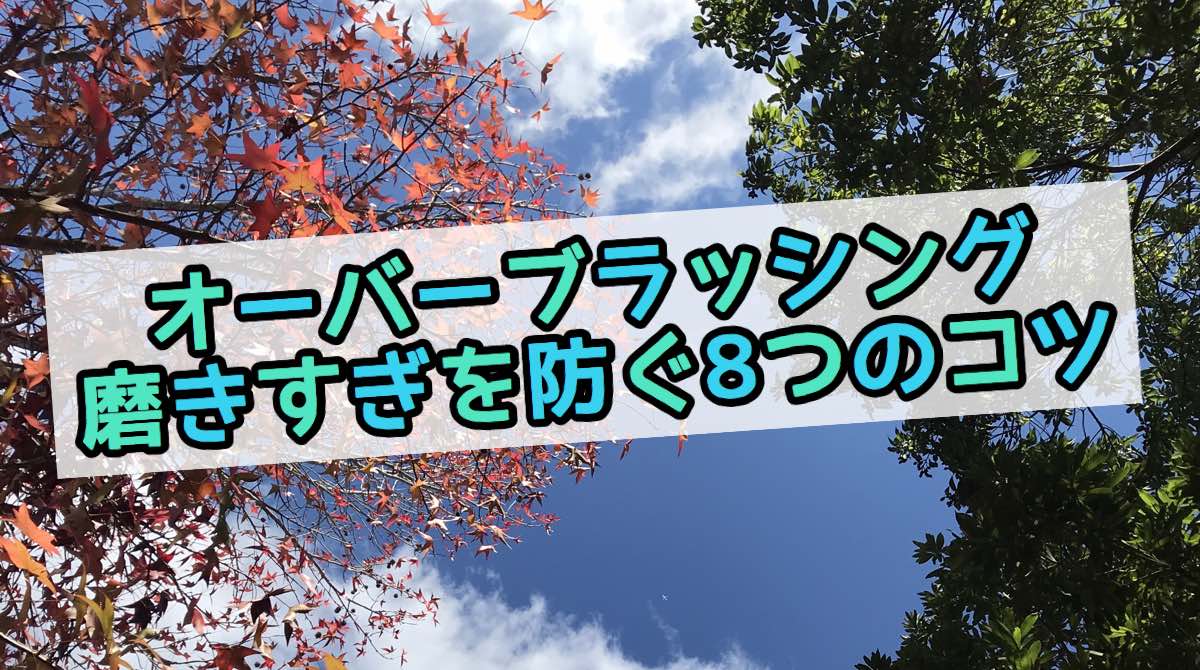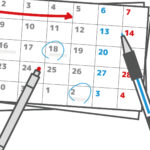歯の表面にくっついているプラーク・歯垢の硬さは、豆腐かチーズくらい。
プラークは、歯ブラシや歯間ブラシ・フロスなどを適切に使うことができれば十分に除去できます。
とはいえ、歯は28本、歯の面の数にすると128面、それらの中にでこぼこがあって、複雑なかたちになっているため、ハミガキはけっこう難しい。。。
さらに、歯ブラシをみがくべきところに
「適度な強さで」
「適切に当てる」
「細かく動かす」
という3点に気をつけなければならないので、
ハミガキというものはかなり高度なテクニックが要求されます。
これら3点はいずれも難しいわけですが、その中でも最も難しいと感じるのは、
力のコントロールです。
上手にみがけるようになっても問題になってくるのが、オーバーブラッシングだからです。
オーバーブラッシングとは、ハミガキのときに歯や歯ぐきハブラシを強く当て過ぎたりみがきすぎたりする状態のこと。
過剰な力がかかりすぎた不適切なオーバーブラッシングは、歯と歯ぐきにダメージを与えてしまいます。
オーバーブラッシングで生じるトラブルについてあげてみると〜
↓
・歯ぐきにみがき傷がつく(擦過傷)
・歯ぐきが削れる(歯肉退縮)
・歯の根の表面が削れ凹む(歯の摩耗)
・歯がしみやすくなる(象牙質知覚過敏症)
・ハブラシの毛先が1−2週間で開いてくる
などがあります。
オーバーブラッシングは、ハミガキに意識高い系の方だけに起こりやすい問題というイメージですが、そうでもありません。
適切に歯に当てられておらず、あまりうまくハミガキできていない方でも、過剰な強い力で、豪快で不適切な動きでハミガキしておれば、オーバーブラッシングになりえます。
また、右利きの人は右側の外側(頬側)の面を強くみがきがち、内側(舌側)の面はハブラシを当てるづらいなどの傾向があり、くちの中の部位によってもオーバーブラッシングとアンダーブラッシングが「まだら」に混在しています。
誰にでも起こりえるオーバーブラッシング。
歯や歯ぐきのトラブルにつながるので、ぜひ防ぎたいところです。
今回は、オーバーブラッシングの防ぐコツについて具体的にご説明していきます。
コンテンツ
コツ1:ハブラシの持ち方は「ペングリップ」で
ハブラシの柄を「グー」で握ると、力が入りすぎ、また細かい動きが難しくなります。
ハブラシはえんぴつを持つように「ペングリップ」で持つと、適度に力が抜け、また細かく動かしやすくなります。
コツ2:歯1−2本ずつ細かく磨く
ハブラシの動かし方は、歯を1−2本を磨く細かい動きで。
豪快にシャカシャカ音がなるくらい大幅に動かすのはやりすぎで、音の割にプラークが取れませんし、オーバーブラッシングとなります。
コツ3:ハブラシの毛は「ふつう」か「やわらかい」ものを選ぶ
ハブラシの毛の硬さは、
「やわらかい」
「ふつう」
「かたい」
がありますが、「かたい」は相当みがく力が弱い方以外はオススメしません。
「ふつう」か「やわらかい」を選んでください。
さらに、毛足の長いハブラシや、極細毛のハブラシを選ぶと、よりソフトな力で当たるようになります。
コツ4:ハミガキの回数は1日2−3回まで
オーバーブラッシングといえば、力に注目されがちですが、みがく回数も注意したいです。
「毎回、何か口にするたびに、ハミガキしてます!1日5回以上!」
という人は、ハミガキ回数多すぎです。
むし歯・歯周病の原因であるプラークは、1日2−3回のブラッシングで十分にとることができます。
コツ5:明るい場所で、鏡で確認しながらみがく
洗面所は意外に鏡が遠くて、暗かったりします。
リビングテーブルの上にメイク用の置き鏡を置くと、明るいし距離も近いので口の中がよく見えます。
明るい場所で、鏡で確認しながらよく見える状態でハミガキをすると、
ハブラシの当たり具合がよく分かるので、無駄なくよくみがけます。
コツ6:過剰圧防止センサーつきハブラシを使う
いろいろ工夫をしても、一生懸命がんばってハミガキすると、ついつい力が入りがちになります。
ハブラシを歯に当てる強さは200g重以下が適切と言われていますが、
「力を抜いて磨いて!」と言われても、ついつい力は入ってしまいます。
ということで、便利な道具に頼るのもありです。
電動歯ブラシの中には、中級クラス以上のものには、過剰圧防止センサーつきのものがあります。
例えば、こちらなど。
↓
無理な力がかかると、光って教えてくれる機能が付いています。
また、最近、手みがき用ハブラシでも過剰圧防止機構のついたものがありますので、お手頃に使えます。
↓
無理な力がかかると、「カチ」っと音がして、歯ブラシの接触圧が適切になるように歯ブラシハンドルがたわむスグレモノです。
コツ7:超幅広ハブラシを使う。
最近流行りの超幅広のハブラシを使うというのもアリです。
例えば、これ。
↓
歯に当たる面が大きくなるので、単位面積あたりにかかる力が分散し減ります。
オーバーブラッシングを防ぐためにはよいでしょう。
ハブラシ選びの基本は、ヘッドがコンパクト、3列くらいのふつうかやわらかい毛、柄はシンプルにまっすぐ、というのをくつがえす幅広ハブラシ。
とある報告では、幅広ハブラシのプラーク除去効率は普通のハブラシと変わらないものの、使用感の満足度は高いとのこと。
実際に、売上も伸び続けているようで、多くの幅広ハブラシが販売されています。
以前、私もブログ記事でまとめたことがありますのでご参照くださいませ。
↓
幅広歯ブラシという選択について

コツ8:利き手と反対の手でみがく
利き手と反対の手でみがくというのもありです。
反対の手でみがくといつもの磨きぐせが出ず、意識してみがけます。
ただし、ちょっぴりハードルは高めですね(笑)
さいごに
以上、8つのオーバーブラッシングを防ぐコツを紹介しました。
これらと合わせて、歯科医院での診察時に、オーバーブラッシングの兆候が歯や歯ぐきにあらわれていないかをチェックしてもらいつつ、ハブラシ方法の確認・説明を受けるのが良いですね。
オーバーブラッシングを防ぎつつ、しっかりハミガキして毎日楽しくすごしましょう!