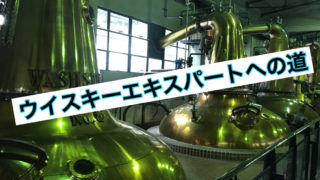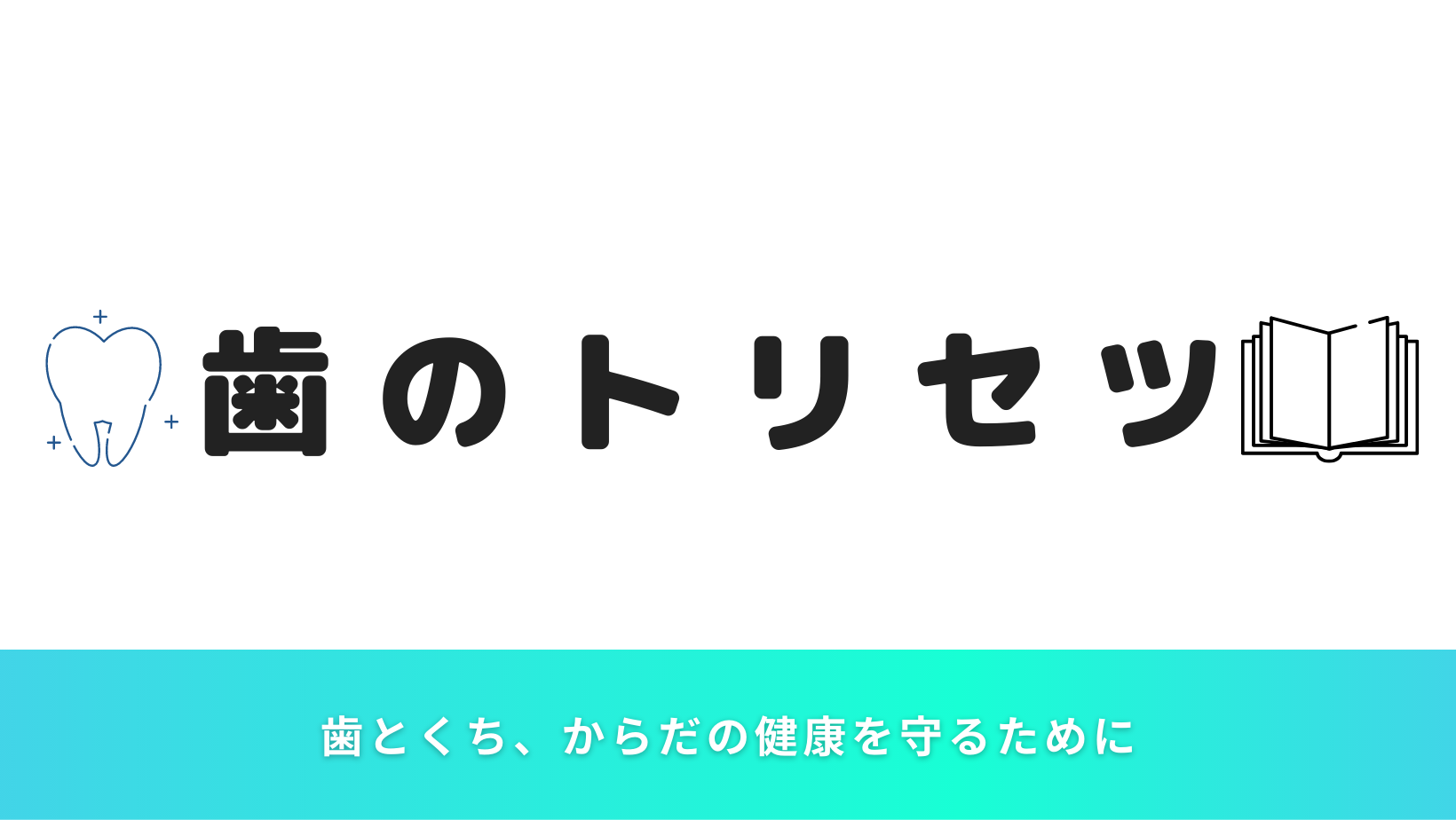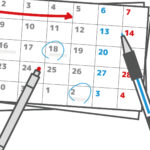こんにちは!
2019年10月27日(日)はウイスキーエキスパートエキスパート試験でした。
私は大阪会場で受験しましたが、会場がある茶屋町のロフト周囲はハロウィン仮装をした楽しそうな人にあふれていました。
さて、ウイスキーエキスパート試験の結果発表はまだですが、試験のインプレッションを忘れないうちにまとめておこうと思います。
問題の傾向は、過去問とほぼ変わりありません。
問題は選択問題100問で、時間は90分あります。
1周するのに私の場合は45分くらいで、あとは見直しに費やすことができたので、ウイスキー検定2級を受けたときほど焦ることはありませんでした。
(ちなみにウイスキー検定2級は選択問題100問で60分なので、わりと時間ぴったりの印象です。)
ウイスキー検定2級と、ウイスキーエキスパートの試験問題の難易度を比較すると、もちろんウイスキーエキスパートの方が難なわけですが、本当に理解しているかを問うてきます。
ウイスキー検定であれば、過去問と全く同じ問題が出題されることもしばしばあるものの、ウイスキーエキスパート試験は、同じ範囲を聞いてくるものの、聞き方を変えてくるので、要注意です。
例えば、年代とイベントに関する年表問題であれば、過去問なら年が問題になっていた一方で、今年はイベント内容を聞いてきたり、そのイベントに関する派生イベントについて問うてきたりされました。
過去問でよく聞かれる年代、イベントについて、よく理解しておき、どこに穴をあけられても埋められるようにしておくとバッチリです。
印象では、過去問的な問題が7割、新傾向や新規蒸留所・トピックについて聞いてくる問題が3割といったところ。
過去問5〜7年分くらいをベースに勉強しておれば不安はないかと思います。
(会場では直近3年分の過去問集1冊を手にしている方も多くおられましたが、私は3年分では傾向がつかめず不安でした。)
もっとも苦しめられた問題は、
「この5つの文章の中で、正しいものの個数を答えなさい」
というもの。
今年はこの「何個正しいか?」問題が5-6問出たので、ハードでした。
知人のウイスキープロフェッショナルホルダーの方にも聞いてみましたが、
「何個正しいか?問題は、はっきりいって正解するのはかなり難しい。」
とのこと。
1つでもわからないトピックが入っていると、答えようがないので、最凶問題といえるでしょう。
ウイスキー蒸留所については、ディアジオとペルノリカールは全て所在地域・特色を踏まえておき、ほかはよく出てくるブレンド関係の蒸留所、ボトラーズの蒸留所など、過去問ででてきたもについても覚えておくのが最低ラインといえます。(これを怠ると、スコッチ、アイリッシュ、アメリカン、カナダの範囲で特典するのが難しくなります。)
5〜7年分の過去問、公式試験対策講座傾向をつかみ、過去問と全く同じ問題が出たら100点をとれるようする。
そして、コニサー教本上下、新版ウイスキー検定教本で知識を深め、さらにウイスキーガロアや土屋守先生のブログで新規トピックを取り入れておくと、80点くらい取れると思います。
さて、あとは合否通知を待つだけ。。。
例年では11月15日前後に通知が届くようなので、ドキドキしながら、ウイスキーを飲みながら、楽しみながら待つことにしましょう。
それではまた!
次の記事はこちら!合否やいかに!?
↓

前の記事はこちら!
↓